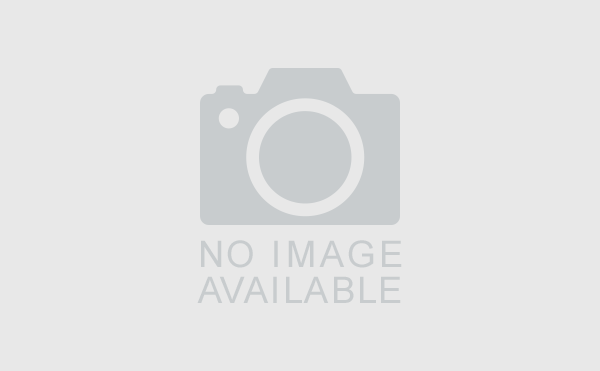日本語の起源はどこなのか?
日本語は他の国の言語とは違い、島国ならではのユニークな言語と言われています。
大陸の言語ではそれぞれの言語が混ざり合い変化していきますが、日本は島国であり他国との接触が少ないことからそういった影響を受けてこなかったと考えられます。
それでは、日本語はどこから発生した言語なのでしょうか?
ということを明らかにするヒントになりそうな研究が今回ご紹介する研究です。
日本語の起源はどこなのか?

日本の歴史を見てみると中国との貿易などの話がよく出てくることは、みなさん中学校などでも習ったかと思います。
しかし、言語の話になるともっとそういった文化的な話よりももっと昔にまで遡らなければなりません。
言語を語族として分類すると
言語には生物学の進化系統樹のように分類がされています。
冒頭でお話した日本語と中国語は実は違う系統に属しています。
日本語は、トランスユーラシア言語と呼ばれる語族に属します。
トランスユーラシア言語に属する他の言語には以下の言語が含まれます。
トルコ語族、モンゴル語族、ツングース語族、朝鮮語族、日本語族
これらは語族というだけあって、さらに分解することができます。
いわゆる方言というやつです。
日本語では、東北弁や関西弁など色々あることは皆さんご承知の通り。
この通り、語族で分類したときに日本語と中国語では語源が違うということが明らかなのがわかります。
驚きなのは、同じトランスユーラシア言語でも中東に属するトルコ語族もあれば、極東アジアの日本語族もあるということ。
アジア大陸の8,000km以上にも及ぶ地域で使われているのがトランスユーラシア語族なんです。
イスタンブールもシベリアも東京も同じトランスユーラシア語族を使っているなんてなんだか不思議じゃないですか?
それではどこからどのようにしてこの言語が広まっていったのでしょうか?
言語の広がりには2つの説が提唱されています。
放浪型の牧畜民説

初期のトランスユーラシア人は、中央アジアに代表的なテュルク系・ツングース系・モンゴル系といった人々のように、主に牛や羊、馬を飼う放浪型の遊牧民として生活し、言語も遊牧民が遠方に伝えていった。
というのが一つ目の説。
定住型の農民説

もう一つの説は、初期の日本人や韓国人、中国人などのように、穀物や豆類、養豚を中心とした定住型の農民が遠方に言語を広めていったという説。
どちらの説が正しいのでしょうか?
3つの学問を融合させて言語の起源を明らかにする

今回紹介する研究は、言語学・考古学・遺伝学という文系理系を跨いだ学問が協力して1つの問題を解き明かそうという試み。
言語学的アプローチ
まずは言語学的なアプローチからトランスユーラシア言語の起源を探っていきましょう。
言語学の分野でよく使われる分類法としてベイズ法というものがあります。
ベイズ法は、それぞれの語族の言葉(水や米などその語族で使われる言葉)や方言といった情報から発音や言葉のパターンなどを解析することで、どの語族とどの語族が近いものなのかを明らかにする手法です。
ベイズ法を利用することで、言語の系統樹を作ることができます。
実際に作った系統樹がこちら

なんじゃこりゃー
と思ったあなた。大丈夫です。
この系統樹では、方言までも分類しているので今回お話する日本語の語源を考えていくにあたってわかっていただきたいのは、一番上のくくりが日本語、2番目が韓国語、そのほかがその他であるということです。
ここからわかることは、日本語と韓国語は比較的近い言語であるということです。
また、日本語の語源を知る上で重要な一番起源となる分岐点、つまり日本語や韓国語とその他の言語が分岐した時点というのが約9,000年前ということが明らかとなりました。
中国の文化が日本に伝わるなんていう最近の話ではなく、めちゃくちゃ昔ということです。
地理的な情報も入れて分類する
ベイズ法による言語学の分類に加えて、地理学的な情報も統計に加えると、9,000年前に分岐した場所もある程度特定することができます。
その結果、韓国の北部に位置する西遼河周辺が起源であるということが明らかとなりました。

時代としては、新石器時代に西遼河周辺で日本語の語源となった言語が使われていたと推定できます。
この言語が青銅器時代に朝鮮半島から九州に伝わったと言語学の観点からは推定することができたのです。
下図の5番の位置が日本語の起源と考えられ、朝鮮語族と日本語族ではどちらかというと日本語族に近い言語が話されていたと筆者らは述べています。

さらに、農業や牧畜に関する言葉がその後の時代まで引き継がれているということもわかり、この結果から定住型の農民が移動していくことで言語が広がったという定住型の農民説が有力な仮説となってきました。
言語学的アプローチの結果をまとめると、西遼河周辺で使われていた農業や牧畜に関する言語が、移住によって朝鮮半島・日本(九州)に渡っていくことで今の日本語として変化してきたと考えられます。
考古学的アプローチ
2点目のアプローチは考古学的アプローチです。
考古学は、遺跡や骨などの過去の遺物から様々なことを推定する学問で、現存の遺跡の特徴(建物の形や土器の形状など)に関するスコアリングや農作物の炭素年代測定を用いてその広がりを検証しました。
建造物の類似性や雑穀類に関する農業器具などの情報から最良盆地周辺でこれらの技術が発達していたことが明らかとなり、言語学的アプローチの結果同様、西遼盆地周辺が起源であるというデータが示されたんです。

ちなみに米はこの場所が起源じゃないみたい
ちなみに今回の検証結果から西遼盆地で誕生した雑穀農業は東アジアに広がっていったと考えられ、一方西アジア(トルコなど)には動物の家畜化や酪農といった文化が伝わっていったと考えられています。
遺伝学的アプローチ
言語学や考古学の観点から、言語や農業といった文化が西遼河周辺から東アジアに伝わっていったということが明らかとなりましたが、その当時の人々の遺伝情報はその通りに分布しているのでしょうか。
これを遺伝学的アプローチでも解析しています。

我らが生物学の登場やね
まずはゲノム情報の解析結果からお示ししましょう。

左図の右下にあるバーはゲノム情報の古さを示しています。
左(赤)になるほど古い遺伝子で、右(緑)になるほど新しい遺伝子になります。
この結果を見てみると、西遼盆地のあたりの人々の遺伝子はより古い遺伝子を持っているということがわかります。
そして、この遺伝子はアムール川流域の人々が持っている遺伝子と言われています。
つまり、アムール川流域の人々の遺伝子を持った人々が新石器時代に西遼河流域に定住していたということになります。
さらに青銅器時代になると、黄河流域の人々の遺伝子が西遼河流域にも見られるようになり、この時代になると人種間の交雑が進んでいったというふうに考えられます。
しかし、現状では初期の新石器時代の西遼河周辺の人骨はまだ見つかっておらず、正直遺伝学的アプローチはまだまだ未完成な結果であると言わざるを得ませんなぁ。

西遼河が起源であるのであれば、ゲノム情報もここを起源として日本に広がっていったという結果が出るのが、言語学と考古学の結果にマッチするよね?

それが必ずしもそうである必要はないと思うのね。実際、
日本人には、アムール系の遺伝情報はほとんど入っていない。
まとめ

3つの学問の結果をまとめると、言語学的(+地理学)な解析によって言語のトランスユーラシア語族の祖先は西遼河流域で発生したということが示唆され、考古学的観点からも確かに農業などの文化も西遼河を起点として東アジアに広がっており、農業に関する言葉伝わっているという点でも一致する部分が大きい。
正直、遺伝学的アプローチに関しては必要なかった気もします。笑

遺伝学役立たんかったやないかーい!